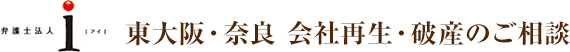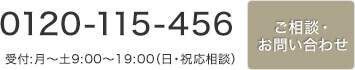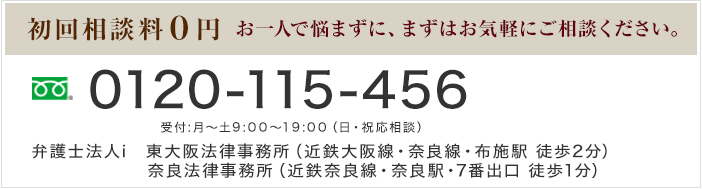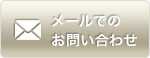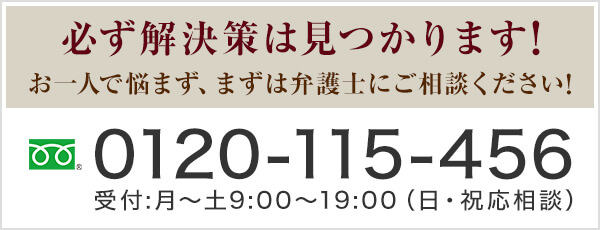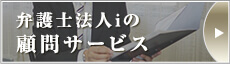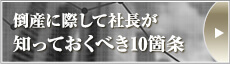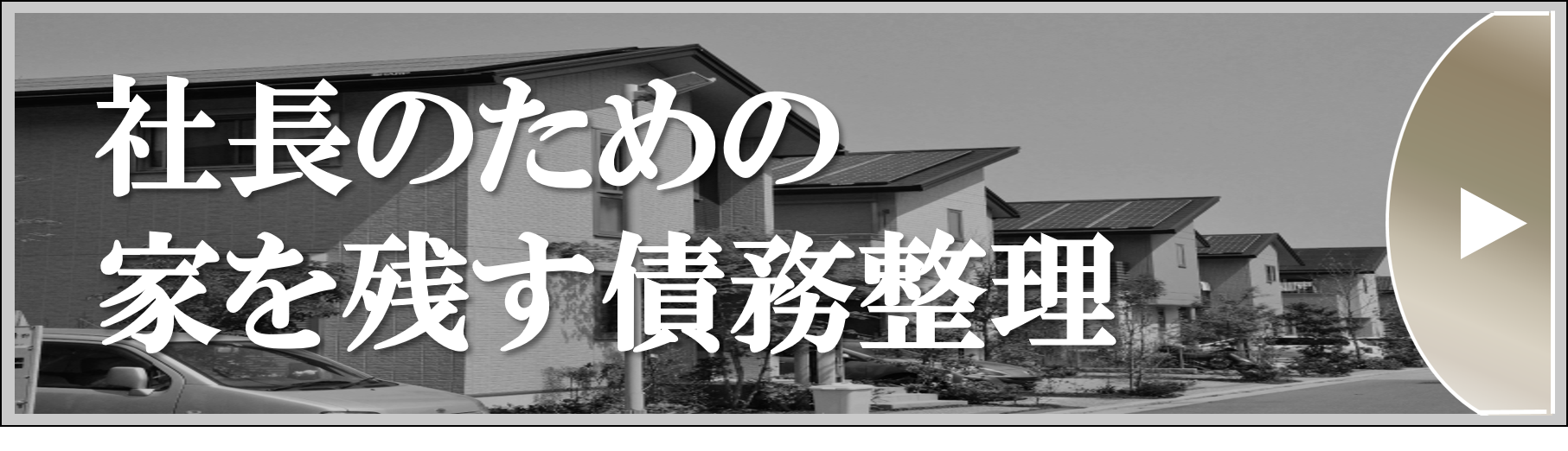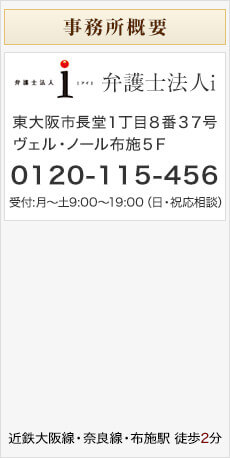【徹底解説】会社が倒産した場合、社員は当然に解雇されるのか?
Contents
倒産=即日解雇は本当か?労働者保護の基本を解説
「会社が倒産した」と聞いて多くの人が連想するのは、「明日から仕事がなくなるのでは」という不安ではないでしょうか。
特に生活費の確保が困難になることや、退職金や給与の未払いが生じるのではないかという懸念が強くなります。
確かに経営破綻という状況は深刻であり、企業の資金繰りが悪化し、支払義務の履行が困難になる場合もあります。
しかしながら、実際には破産手続が開始されたからといって、必ずしも即日解雇になるとは限りません。
破産法や労働基準法などの関連法令により、会社が社員を解雇する際には、いくつかの条件と手続きを遵守する必要があります。
具体的には、労働基準法第20条に基づき、会社は原則として30日前に解雇予告を行うか、もしくは30日分以上の平均賃金を支払う(解雇予告手当)義務があります。
この手当は、労働者の生活を守るための保護措置であり、たとえ会社が破産状態にあっても、法的に免責されるわけではありません。
また、社員が労働基準監督署に申し立てを行うことで、会社の対応が適法であったかどうかが審査されることもあります。
さらに、企業が倒産手続きをとる場合でも、財団債権としての賃金や解雇予告手当が支払われる仕組みがあり、一定の救済措置も講じられています。
したがって、「倒産=即時解雇」という図式は、すべてのケースに当てはまるわけではなく、法的保護と手続の存在によって、労働者の権利が一定程度保護されています。
倒産後、社員の雇用はどうなるのか?
解雇通知と退職の法的処理
倒産手続により法人格が消滅すれば、会社は従来どおり雇用契約を継続することができなくなります。
基本的には、すべての社員との労働契約が終了することとなり、解雇通知が発せられます。
したがって、この通知を受けた社員は、法的にも実質的にも退職扱いとなり、失業保険などの申請準備に移行することになります。
事業譲渡・M&Aによる雇用維持の可能性
実際には倒産の手続がどのような形で進行するか、企業の資産状況や再建計画の有無によって、社員の処遇は多様化します。
たとえば、会社が保有する一部の事業や部門を他の企業に譲渡する「事業譲渡」や、第三者のスポンサーが再建を支援する「スポンサー型M&A」によって、社員の一部が新たな雇用主に引き継がれるケースもあります。
この場合、雇用が継続され、労働条件も維持されることが多いため、解雇や退職といった形を取らずに済むメリットがあります。
任意整理・私的整理(事業再生)による再建と雇用調整
上記の他に、裁判所を通じた法的整理ではなく、私的に債権者と交渉する「任意整理」や「私的整理」が選択される場合、会社は一定の期間事業を縮小しつつも営業を続け、再建の道を模索することができます。
こうした整理方法は、柔軟な対応がしやすいという利点があり、雇用の維持や段階的な人員整理といった措置が取りやすくなります。
この際、必要に応じて労働組合や社員の代表と協議を行い、誰が残り、誰が退職するかについての交渉が行われることが一般的です。
破産管財人による一部雇用の継続と給与支払
破産申立てが行われた場合には、裁判所が選任する破産管財人が企業資産の管理・回収・売却を実施しますが、その過程で一定の清算業務や書類整備が必要となるため、社員の中から一部を暫定的に雇用し続けることがあります。
こうした雇用関係における給与は、破産財団の必要経費として分類される「財団債権」に該当し、優先的に支払われることになります。
これにより、労働者の生活基盤の一部を確保する救済策が講じられるのです。
一方で、事業継続や再建が困難と判断された場合には、すべての社員が解雇される可能性も高くなります。
このような状況では、労働者は退職証明書の交付を受け、雇用保険の申請や未払賃金立替制度の利用を検討する必要があります。
解雇に際しては、法律上の解雇予告や手当の支給が原則として義務付けられており、これらが不履行であった場合には、労働基準監督署への相談も視野に入れるべきです。
いずれの手続においても、会社の倒産は労働者の雇用と生活に重大な影響を及ぼすものであり、状況に応じた冷静な判断と迅速な対応が求められます。
自身の雇用状況の確認に加え、再就職や生活支援のための情報収集、法律専門家としての弁護士への相談など、多角的な対応を早期に始めることが、生活再建への第一歩となります。
倒産時の給与・退職金・社会保険の支払と救済制度
未払賃金とその法的順位
倒産時にもっとも懸念されるのが、給与や退職金の未払い問題です。
企業が経営破綻した際には、社員に対する賃金の支払いが滞るケースが多く、そのまま退職せざるを得ない状況になることも少なくありません。
特に月末に支払予定だった給与が払われず、そのまま解雇されるような事態が現実に起こり得ます。
財団債権としての給与・解雇予告手当の優先支給
会社が倒産する前に発生した社員の給与(破産手続開始決定の3か月より前の未払い給料)、退職金(下記)、社会保険料の支払は、破産債権または優先的破産債権(破産法98条1項、民法306条2号)として扱われます。
退職金請求権については、退職前三ヶ月間の給料の総額に相当する部分は財団債権となり(破産法149条2項)、その余の退職金請求権は優先的破産債権となります(破産法98条1項、民法306条2号)。
これに対し、破産手続開始後に発生する給与・破産手続き開始決定の直前3ヶ月間の給料(破産法149条1項)や解雇予告手当(下記)などについては、財団債権として区分され、他の破産債権に優先して支給される対象となります。
解雇予告手当の破産法上の扱いについては、解雇が破産手続開始前に行われた場合には、優先的破産債権にしかなりません。例外的に、破産手続開始後に、破産管財人が解雇をした場合には、財団債権となります(破産法148条1項4号)。
もっとも東京地方裁判所では解雇予告手当について実質的な給料該当性を認め、破産手続開始前3ヶ月間に解雇が行われた場合の解雇予告手当については、破産管財人から財団債権として支払う旨の許可申し立てがあれば、財団債権として支払うことを許可するとの運用をしています。
財団債権とは、破産手続中に管財人によって支払が必要と判断された債権であり、清算中も事業継続が必要な場合や一時的な業務処理に必要な人員の賃金などが該当します。
未払賃金立替払制度の概要と申請方法
退職金の支払いについては、企業の就業規則や個別の労働契約の内容によって取扱いが異なります。
仮に会社に退職金規程が存在していても、資産が著しく不足している場合には、退職金が一部しか支払われない、またはまったく支払われないリスクがあります。
こうしたリスクに備えて、労働者は未払賃金立替払制度の利用を検討することが推奨されます。
この制度は、厚生労働省所管の独立行政法人「労働者健康安全機構」により運営されており、企業倒産後に未払となった給与や退職金について、一定限度額を上限として国が支払う制度です。
この制度を利用するためには、離職票や賃金台帳、労働契約書、就業規則等の提出が必要になります。
失業保険・健康保険の任意継続等の支援策
会社が倒産した後における社員の生活支援策として、健康保険の任意継続や、失業保険(雇用保険)の受給資格についての確認も重要です。
特に失業保険は、自己都合退職と異なり、倒産による会社都合退職では待機期間が短く、早期に支給が開始されるメリットがあります。
ハローワークでは、申請から支給までの流れや、追加的な再就職支援制度についても情報提供を行っており、必要に応じてキャリアカウンセリングなどのサポートも受けられます。
解雇後の就職活動と再就職支援の全体像
解雇通知後にすぐ転職活動を始めてよい理由
社員が会社より解雇通知を受けた時点で、法的には退職が確定したとみなされ、就職活動を始めることが可能です。
これは、労働契約が終了する旨が明確となったためであり、たとえ退職日が将来であっても、就職先の検索や面接活動を開始することが法的にも倫理的にも問題ないとされています。
とりわけ倒産という不可抗力による退職の場合には、社員本人の責任ではないため、転職市場での印象にも大きな影響はありません。
公的支援制度(再就職手当・職業訓練給付金等)
失業保険等、受給資格がある人は、各種の支援策を受けることができます。
具体的には、早期に新たな就職先が決定した場合に支給される「再就職手当」や、職業訓練を受講することで給付される「職業訓練受講給付金」などが代表例です。
これらは、職業安定所(ハローワーク)での手続きを経て利用可能であり、条件を満たせば複数の支援を同時に受けることも可能です。
自治体・ハローワークの就職支援サービス
倒産によって突然の離職を余儀なくされた社員に対しては、行政機関による再就職支援プログラムや、地方自治体が提供する就労支援サービスも存在します。
たとえば、無料職業紹介、キャリアカウンセリング、スキル診断などがあり、それぞれの状況に応じた支援を受けることができます。
倒産時には、会社側からの十分な説明が得られないケースも多いため、自ら積極的に情報を収集する姿勢が求められます。
ハローワークの窓口担当者、弁護士、社会保険労務士などの専門家に相談することは、制度の適用条件や手続きに関する誤解を防ぎ、最適な行動を選択する上で非常に有益です。
面接対策・職務経歴書の準備で差をつける
再就職においては、退職理由をどのように伝えるか、またブランク期間をどう説明するかなども重要なポイントとなります。
必要に応じて専門機関のサポートを受けながら、自身の職歴やスキルを整理し、書類作成や面接対策にも取り組みましょう。
これらの取組みが、早期の再就職や新たなキャリア形成への道を切り拓く大きな鍵となるのです。
専門家に相談すべき理由とそのタイミング
倒産法制に詳しい弁護士の重要性
倒産処理は、労働法・破産法・商法・民事再生法といった複数の法令が絡み合う複雑な手続です。
そのため、的確に状況を判断し、円滑に事態を処理していくには、法律に関する専門的な知識と経験が不可欠です。
経営陣はもちろんのこと、社員側においても、責任の所在を明確にし、自らの権利を適切に理解して対応するためには、弁護士、とりわけ倒産法制に精通し、倒産実務の経験が法務な弁護士による専門的な支援が非常に重要です。
特に、企業が破産手続に入る段階では、社員に対する説明責任が問われます。
適法な手続を行うことで、従業員からの不満や訴訟リスクを回避するだけでなく、破産財団における労務費の負担や優先弁済義務の整理も円滑に行うことができるようになります。
これにより、無用な法的トラブルの発生またはその拡大を防ぐことができるのです。
会社が所有する不動産・機械設備・売掛金などの資産についても、回収や清算を巡って債権者とのトラブルが生じやすくなります。
これらの問題に迅速かつ適切に対処するためには、破産法の理解はもちろん、交渉術や経済的知見を有する法律専門家としての弁護士によるサポートを受けることが確実な方法であるといえます。
必要に応じて、資産の保全処分、債権の調査確定、労働債権の整理など、具体的な手続きを確実に踏んでいく必要があります。
弁護士は、経営者に対しては破産手続の申立準備、財産目録の作成、債権者集会対応、さらには労働者への通知義務の履行について助言を行うことができます。
また、従業員側にも、再就職活動に向けた助言、退職手当や未払賃金の立替制度の利用方法、ハローワーク等への申請手続きなどについて実務的な支援を行うことが可能です。
倒産処理を円滑に行うためには、単なる法律の知識だけでなく、労使双方の視点に立ったバランスの取れた対応が求められます。
そのためにも、倒産法制に詳しい弁護士の早期関与と継続的なサポートは、経営者と従業員双方にとって欠かせない存在となります。
このように企業の倒産においては、会社側と社員側の双方にとって、法律専門家としての弁護士を早い段階から起用していくことが自らを保護するうえで極めて重要なのです。
まとめ:倒産という危機をどう乗り越えるか
倒産によって生じる不安や混乱を最小限に抑えるためには、できるだけ早期に状況を把握し、具体的な対応策を講じることが不可欠です。
まず、会社からの通知や予告があった際には、その内容をしっかりと確認し、解雇や退職の時期、給与や退職金の支払予定、保険や年金の手続きについての情報を確実に得るようにしましょう。
特に倒産の場合、通常の退職とは異なり、未払賃金や解雇予告手当の支給に関する問題が生じやすいため、労働者一人ひとりが自らの権利や救済制度について把握しておくことが重要です。
たとえば、「未払賃金立替払制度」や失業給付、再就職支援など、公的な支援制度は数多く用意されています。
こうした制度は、専門家の助言を受けることでスムーズに利用することが可能になります。
加えて、再就職を見据えた行動も重要です。
倒産が確定した段階で就職活動を開始することにより、ブランク期間を短縮し、生活の安定を早期に取り戻すことができます。
ハローワークや自治体の就労支援センターでは、求人情報の提供に加えて、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策なども行っており、積極的に活用することが望まれます。
不透明な状況においては、不安が先行して冷静な判断を失いやすくなりますが、正確な情報に基づいた冷静な判断と行動こそが、将来の不安を払拭し、新たな一歩を踏み出す原動力になります。
倒産という苦境に直面したとしても、制度を正しく理解し、専門家と連携しながら、次のキャリアや生活基盤を着実に築いていくことが、労働者にとって最も大切な行動指針となるでしょう。
参照ページ
従業員に対する対応 | 東大阪・奈良 会社再生・破産のご相談(弁護士法人i)
No.14 破産申立 ⇒ 東日本大震災以降、様々な要因で廃業に追い込まれた事例 | 東大阪・奈良 会社再生・破産のご相談(弁護士法人i)
NO.21 破産申立 ⇒ 会社の破産と従業員の未払給与 | 東大阪・奈良 会社再生・破産のご相談(弁護士法人i)
NO.25 破産申立 ⇒ 会社破産とアルバイトの未払給与 | 東大阪・奈良 会社再生・破産のご相談(弁護士法人i)
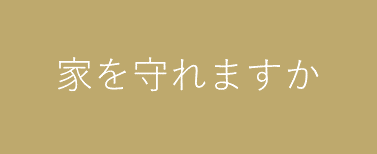 |
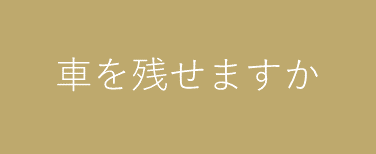 |
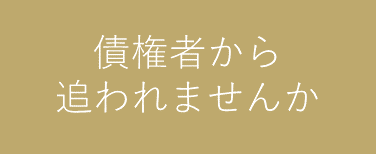 |
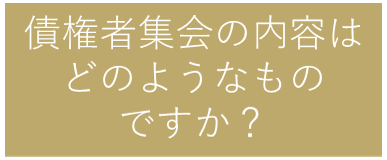 |
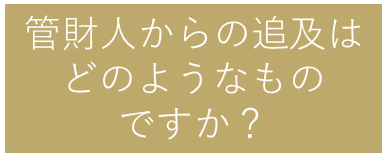 |
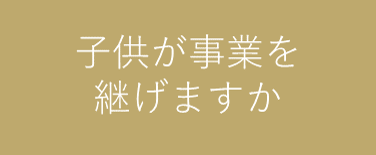 |
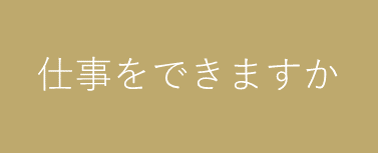 |
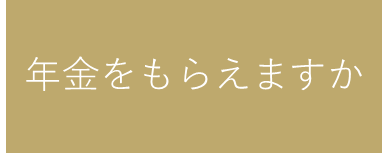 |
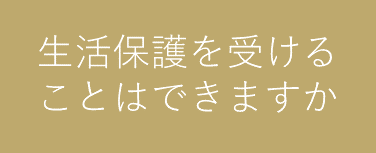 |
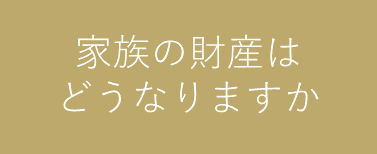 |
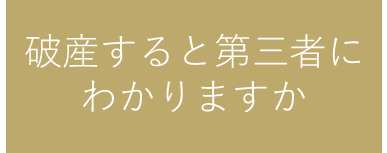 |
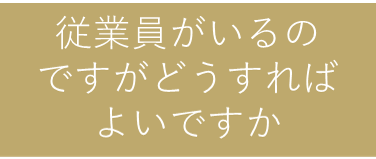 |
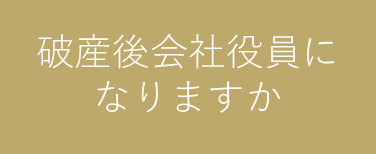 |
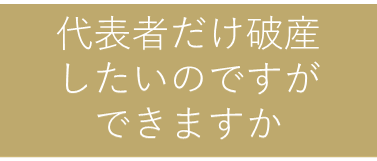 |
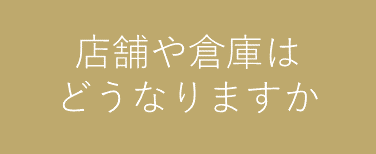 |
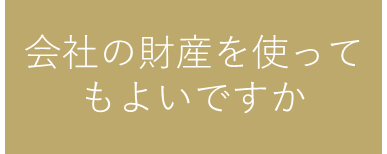 |
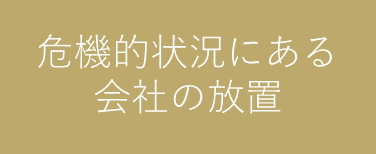 |
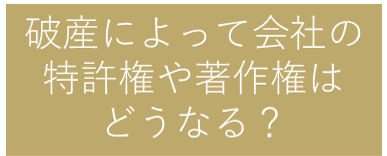 |
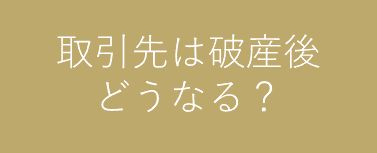 |
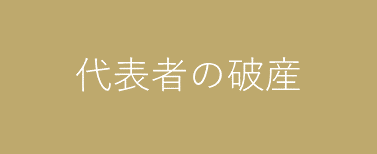 |
- 「自己破産するとカーリース契約はどうなる?会社・個人別に解説」
- 【徹底解説】会社が倒産した場合、社員は当然に解雇されるのか?
- 仕事をできますか
- 代表者だけ破産したいのですができますか
- 代表者の破産
- 会社の財産を使ってもよいですか(使ってしまったのですが大丈夫ですか)
- 債権者から追われませんか
- 債権者集会の内容はどのようなものですか
- 危機的状況にある会社の放置
- 取引先は破産後どうなる?
- 子供が事業を継げますか
- 家族の財産はどうなりますか
- 年金をもらえますか
- 店舗や倉庫はどうなりますか
- 法人代表者の死亡
- 生活保護を受けることはできますか
- 破産すると第三者にわかりますか
- 破産によって会社の特許権や著作権はどうなる?
- 破産後会社役員になりますか
- 社長が破産、家や家族はどうなる?弁護士に聞く、財産を守るための方法
- 管財人から追求はどのようなものですか
この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士
黒田 充宏
法人破産は自己破産と違い、従業員対応や債権者などへの交渉、説得が必要となってきますので、経験豊富な事務所に依頼されることをお勧めします。破産をお考えの方の中には、破産費用が払えないから相談に行くのをためらわれている方もいらっしゃると思いますが、当事務所はこれまでに850件以上もの借金に関するトラブルの事件処理を担当し、会社の倒産・再生の相談や事件処理も100社以上担当してきた経験から、手元に現金がなくても、住宅や車を売却することによって、破産費用を充足した例がたくさんあります。
破産についての相談は、無料で対応しておりますので、費用が払えないかもしれないと思っていらっしゃる方も一度弁護士に相談してください。原則代表弁護士が面談します。あなたの状況に応じた借金問題の解決方法をご提案いたします。